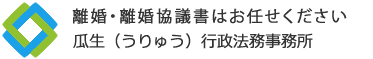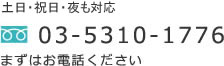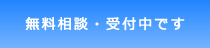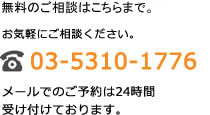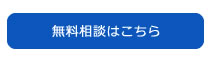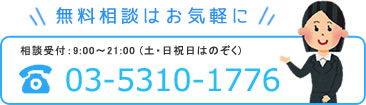よくある質問 相談について
よくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? |
|
お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 |


相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
|
まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |


昼間は勤めがありますので、夜でも相談はできますか? |
|
ご予約をいただけましたら、大丈夫です。 今までも、夕方からのご相談、あるいは、夜のご相談を数多く対応して参りました。 遠慮なく、ぜひご相談くださいませ。 |


平日は仕事が忙しいのですが、土日でも相談することができますか? |
|
事前にご予約をいただけましたら、土日も対応させていただきます。 お勤めの方など、土日しかお時間がない方も多いですから、土日もお会いして、または、お電話でのご相談に対応しております。 ご遠慮なく、ご連絡くださいませ。 |


会社が忙しくて、土日もあまり時間が取れないのですが、平日の会社帰りに、貴事務所まで行かなくても、何処かでお会いして、相談することはできますか? |
|
大丈夫です。 会社帰りにということでしたら、私がご都合の良い駅まで伺うこともできます。 良くあるケースですから、ご遠慮なく、ご要望をお伝えください。 |


ちょっと遠いのですが、出張はどこまでしてもらえますか? |
|
遠方の場合でもご対応させて頂いております。まずはご相談いただけましたら幸いです。 私が利用している杉並区の荻窪駅はJRの他、地下鉄東西線が通り、丸ノ内線の始発駅でもあります。 都内でしたら、地下鉄を使うと思っていたほど、移動に時間が掛かりません。そのため、都内の色々な場所へ伺っております(最近は、銀座、虎ノ門、新橋や、浅草、北千住などの下町、八王子などの多摩地区など)。 東京都内はご対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。フットワークの軽さが、私の大きな特徴です。 |
離婚・公正証書について
どのようにして離婚協議書を作るのですか? |
|
ご依頼によって、色々なケースがあり、離婚協議書を作成する過程も様々ですが、1例をご紹介しましょう。 「お電話かメールでご連絡をいただいた後、一度、ある程度時間を取って、お電話でお話をして、ご事情をお聞きしたいです。 お電話は、夜、土日など、依頼者様のご都合に対応できますので、ご安心ください。 その後、できればお会いして、離婚協議書の内容について、具体的にお話をしたいです。 その先は、電話・メールでご連絡を取りながら、離婚協議書を作成できることが、通常です。」 |

離婚することには合意しましたが、養育費などの約束は、これから話し合います。 離婚協議書か公正証書を作りたいと思っていますが、具体的には、まだ何も決まっていませんが、相談に乗ってもらえますか? |
|
具体的な話し合いはこれからするというときでも、ご相談にお乗りいたします。 話し合いの前に、ご相談いただくことは、事前準備ができますから、プラスも多いかと思います。 |

初めての相談に行くには、戸籍などの資料を持参した方がいいですか? |
|
もちろん、戸籍等をお持ちでしたら、お持ちください。その他、お持ちになりたい資料がありましたら、お持ちください。 ただ、初めてのご相談では、特に資料は要らないと思って頂いて構いません。初めからご負担が重くなっても困りますから。 |

離婚することに合意して、離婚協議書か、公正証書を作りたいと思っています。養育費や慰謝料についても大雑把ですが合意はできていると思います。しかし、この先、何をどのように決めればいいのかが分かりません。 相談に乗ってもらえますか? |
|
離婚の合意をして、話し合いをしているけど、「何を、どのように決めればいいのかが分からない。」というケースも多いですね。 私が連絡をいただくお話では、養育費の額などの基本的なご希望が決まっていることも多いです。そうすると、その他のご事情やお考えもお聞きして、私は、その方用のご参考資料を作ります。 ご参考資料を作る目的は、離婚の際の約束について具体的なイメージを持っていただくこと、および、お考えをまとめるためのお手伝いをすることにあります。 この資料には、その方のご事情やお考えが含まれていますから、これから先、「何をどのように決めればいいのか」を導き出すための参考になります。 ご参考資料を基にして、私は2時間程度お話をすることが多いのですが、離婚協議書や、公正証書を作るために考えること、決めることが具体的に分かってきます。 このようなお手伝いもしておりますので、どうぞご相談ください。
|

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
|
公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |

養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
|
養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |

離婚では、どのような時に、公正証書を作っておくべきですか? |
|
公正証書は、期限の決まった金銭の支払いを内容とする約束で、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そこで、離婚について言えば、養育費の支払いについて約束がある場合には、公正証書を作っておくべきですね。その他に、慰謝料の支払いがある、財産分与としてお金の支払いがある場合なども公正証書を作っておくべき場合ですね。
その他にも、公正証書は、公証人が作る公文書で信用力・証明力が強いですから、しっかりした信用性のある証拠を作っておきたい場合にも、公正証書の作成を考えることがあります。最近扱った例では、7年先の退職金についての財産分与の契約を公正証書でしました。これは、強制執行できる契約ではなかったのですが、奥様がしっかりとした契約を信用性の強い公正証書ですることを希望されたのです。将来の紛争を未然に防止しようとされたのです。
公正証書の作成についてお悩みであれば、ご相談くださいませ。
|

離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか? |
|
公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。 そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。 他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。 慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。
|

離婚するのですが、財産分与として金銭の支払いがあります。このような場合も、公正証書を作るべきでしょうか? |
|
公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そうすると、財産分与としての金銭の支払いが、離婚前に済むのであれば、支払が滞ることはありませんから、公正証書を作成する必要はありませんね。 他方、財産分与としての金銭の支払いが、離婚後となるのであれば(一括払いでも、分割払いでも)、支払が滞るおそれがありますから、公正証書を作成しておく必要があります。 |

養育費の約束を決めるので迷っています。 養育費の支払いは、20歳までと決まっているのですか? |
|
養育費の支払いは、20歳までとは決まっていません。 その他の年齢で決めることもありますし、年齢ではなく高校や大学の卒業を考慮して決めることもあります。 「養育費をいつまで支払うのか?」については、色々な決め方がありますから、迷われたらご相談ください。 |

協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |
|
お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。
最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |

離婚するので、子どもの養育費の額について話し合っていますが、主人の年収が毎年一定ではなく、かなり変動があります。 このような場合、どのようにして、養育費の額を決めればいいですか? |
|
養育費の額を考える際には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にすることが多いと思います。この算定表は、ご夫婦の年収から、養育費の額を簡易・迅速に算定しようというものですから、ご主人の年収を決める必要があります。 ご主人の年収が変動する場合(会社員では年棒制や歩合の割合が大きいとき、また、自営業者の場合など)には、過去数年間の収入の平均額を計算するなどの方法で、ご主人の収入を決める工夫がされています。 |

【公正証書の内容のご相談】 公正証書を作って離婚しようと思い、主人と養育費の支払期間の話し合いをしていますが、主人は、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っています。 早く公正証書を作って、1日でも早く離婚したいのですが、子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です。 公正証書を作る際の養育費の決め方について、現状を踏まえて、何かアドバイスはありますか? |
|
公正証書で養育費の支払期間を決めるときには、「何時から何時まで支払うのか」を明確に定める必要があります。 早く公正証書を作って離婚したいが、ご主人が、「子どもが高校を卒業するまでしか養育費を払わない」と言っていることからすると、公正証書では、養育費の支払期間は、「お子さんが満18歳になった翌年3月まで」という決め方になるかも知れません。 その上で、「子どもが大学等に進学した場合には、養育費が心配です」というお気持ちにどのように対応するかですが、「お子さんが満18歳になった翌年4月にお子さんが大学等に在学して就学中の場合には、養育費の支払期間の延長、養育費の額について、改めて協議する」旨の条項を公正証書に記載しておくことが考えられます。 少なくとも、養育費の支払期間を延長できる可能性を残しておくことができ、ご主人の現状との兼ね合いとしては、この辺が限度かも知れません。
ただし、上記のような条項に基づいて改めて協議して養育費の支払いを決めた場合には、その間の養育費の支払いは、公正証書外の約束であり、公正証書上は、養育費の額、支払期間などの定めはありませんので、仮に、養育費の支払いが滞っても、強制執行の対象とはなりませんのでご注意ください。 |

離婚するので、公正証書で年金分割をしたいと思っていますが、年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があるようですね。 良く分からないので、ザックリと説明してください。 |
|
「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の加入実績を、離婚するご夫婦が分け合うことです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 この年金分割には、①「3号分割」と②「合意分割」があります。簡単に言うと、2008年4月以降の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするのが「3号分割」で、2008年3月以前を対象とするのが「合意分割」です。 「3号分割」は、会社員の夫に扶養される専業主婦など、国民年金の「第3号被保険者」だった方が対象となります。この方は、年金事務所で手続きをすれば、2008年4月から離婚した月の前月までの厚生年金・共済年金の加入実績のうち、対象となる夫の厚生年金・共済年金の加入実績の「2分の1」の分割を受けることができます。「3号分割」では、ご夫婦で年金分割の合意をすることは不要です。 以上に対して、「合意分割」は、2008年3月以前の厚生年金・共済年金の加入実績を対象とするもので、ご夫婦で協議して分割の割合を決めて年金分割をします。分割の割合については、実務では、通常、厚生年金の加入実績を半分(0.5)ずつにすることが多いと思います。 |

公正証書で、離婚時の年金分割のうち「合意分割」をしたいと思っています。 準備しておいた方がいいことはありますか? |
|
年金分割のうち「合意分割」をご希望でしたら、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しておいてください。「年金分割のための情報通知書」は、請求してから届くまでに3週間~1ヶ月位かかりますし、公正証書を作成するためには必須のものですから。 |

年金分割のうちの「合意分割」を公正証書でしようと思います。 「合意分割」を公正証書でするメリットは何でしょうか? |
|
年金分割のうちの「合意分割」は、ご夫婦で分割の割合を決めてする年金分割ですが(2008年3月以前の厚生年金・共済年金が対象)、その方法としては、離婚後にご夫婦が揃って年金事務所へ行って手続きをする方法、公正証書(協議離婚の場合)や調停証書(家庭裁判所での離婚調停の場合)などで分割の割合を定める方法等があります。 このうち公正証書の場合には(調停証書も同じですが)、離婚後に年金を分割してもらう方(ほとんどは奥さんですね。)が、公正証書を使って、年金事務所でお1人で手続きが出来ることが大きなメリットです。 年金分割の手続きは離婚後にしますが、離婚したご夫婦が離婚後に一緒に年金事務所へ行くというのは、お仕事の忙しいご主人にとっては大きな負担になりますし、顔も合わせたくないご夫婦もいらっしゃいますから。 |

離婚に際して、妻から公正証書で年金分割をするように要求されています。 年金分割をすると、私が将来もらう年金額は半分になるのでしょうか? |
|
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(及び、厚生年金に一元化される以前の共済年金)の加入実績を離婚するご夫婦が分け合う、ということです。これにより、ご夫婦の年金額が調整されます。 注意して頂きたいのは、分割されるのは、婚姻期間中の厚生年金(及び、厚生年金に一元化される以前の共済年金)の加入実績に限られ、婚姻前及び離婚後の厚生年金の加入実績や国民年金は、分割の対象ではありません。 従って、年金分割をしたからと言って、将来もらう年金額が半分になるということはありません。 |

離婚協議書・離婚の公正証書は、いつ作成したらいいですか? |
|
離婚協議書・離婚の公正証書は、離婚届を提出する前に作成するべきです。 理由は複数あります。知りたい方は、下の詳細をクリックしてください。 |

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
|
概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>>
|

離婚することを決めましたが、夫婦ともに働いていて忙しいので、公正証書を作るためにあまり時間を割くことが出来ません。そのため、公証役場へ行く回数も最低限にしたいと思っています。 公正証書を作成するサポートをお願いすると、依頼者は公正証書に署名押印する日だけ公証役場へ行けばいいのでしょうか? |
|
はい。依頼者の方は、公正証書への署名押印の日だけ公証役場へ行っていただければ、公正証書を作ることができます。
【公正証書ができるまでの流れを簡単に記載すると、以下のようになります。】 私は、依頼者の方と連絡を取りながら公正証書の内容を考えますが、その内容が決まると、私が公証役場と連絡を取ります。 公正証書の内容については、公証役場や公証人と、何回か連絡をとることも多いですが、その連絡も私が行います。そして、公証人が公正証書の案文を作成すると、私に送って下さいますから、それをご夫婦で確認していただき、内容に問題がなければ公正証書の内容が決まります。 その後、ご夫婦で日程の調整をしていただいて、公証役場へ予約を入れ、当日、公証役場で署名押印をして公正証書が完成します。
依頼者の方は、公正証書の内容を決めるために私と連絡をとる必要がありますが、公証役場との関係は、連絡を含め全てを私が処理し、依頼者の方は、最後の署名押印の日に、公証役場へ来ていただければ、公正証書を作ることができます。もちろん、公証役場へ行くときには、私も一緒に行き、公正証書の完成を見届けます。
なお、公証役場と連絡を取る際には、戸籍などが必要になりますが、委任状を使って私が取得できる書類は、ご希望であれば、私が取得いたします。 |

平日はパートで働いていて、あまり休めません・・・休みたいと言うと、嫌な顔をされてしまいます。 公正証書を作るためには、何回、公証役場へ行く必要がありますか? |
|
ご自分で手続きをするのであれば、最低でも2回行く必要があります。3回以上行ったというお話もお聞きしました。 |

仕事が忙しく、あまり時間に余裕がありませんが、公正証書を作るための署名押印の日は、公証役場でどれくらい時間がかかりますか? |
|
公証役場で、スムーズに署名押印が済むように、事前の準備は万全を心がけていますが、公証役場で、再度、公正証書の内容の確認をしていただく必要もありますので、30分前後をお考え下さい。 |

公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか? |
|
公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。 |

離婚では、公正証書を作るときに、各自治体から補助があるようですが、どのような制度ですか? |
|
公正証書を作るときには、公証役場に手数料を払う必要があります。この手数料は、養育費の支払い、財産分与、慰謝料などについて、それぞれ計算され、合計額が公証役場へ支払う手数料となります。 各自治体から補助があるのは、このうち、養育費の支払いに関する部分の手数料で、公正証書で養育費を受け取る方が公証役場への手数料を負担した場合に、上限はありますが、各自治体から補助があります。比較的新しい制度ですが、急速に広まり、おそらくほとんどの自治体に、補助・援助の制度があるかと思います。養育費の支払いを含む公正証書の作成をお考えであれば、お住まいの自治体で調べて見てください。 例えば、東京都練馬区での費用助成は、次のようになっています。
|

公正証書を作るために、当方の考えをまとめた、相手方への提案書のようなものを作って頂きたいのですが、可能でしょうか? |
|
はい、そのようなお手伝いもさせて頂きます。 公正証書を作るために相手の方と話をするのであっても、相手の方が具体的なイメージを持てるようにした方が話が進みやすいこともありますね。 また、提案書を作る過程で、ご自身のお考えをまとめることも出来ます。 そのようなご依頼もありますから、お気軽にご連絡ください。 |

主人と離婚の話し合いを進めてきましたが、思うようには進みません。 公正証書を作るために、相手方への提案書のようなものを作って頂けるとのことですが、もう少し詳しく教えてください? |
|
私が良くするのは、今までのお二人の話し合いで合意した事項とご相談者のご希望を踏まえて合意書(案)を作り、分かりにくい点については、簡単なコメントや説明を記載して、相手の方用のご参考資料を作るという方法です。 相手の方は、これを見ることによって、公正証書を作った場合にどのような取り決めとなるかが分かり、受け入れられる事項と受け入れられない事項が明らかになります。そして、何を協議しなければならないか、自分が受け入れることができるのはどこまでか等が明らかになると思います。 お二人の話し合いを進みやすく、また、具体的なものにするための方法と考えています。「公正証書では、どのような取り決めとなるのか」という具体的なイメージを持って協議を進めるべきだと考えています。 |

公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? |
|
代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。 |

公正証書を作るために、公証役場での代理人をお願いできますか? |
|
はい、公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。 公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。 |

離婚するのですが、私(妻)の実の姉を、夫の代理人として公正証書を作ろうと思います。私(妻)の実の姉を代理人として、離婚の公正証書を作ることはできますか? |
|
おそらく、妻の実のお姉さんを夫の代理人として、離婚の公正証書を作ることはできないと思います。 実は、離婚の公正証書を作成する際の代理人については、少し難しい問題があり、それは、離婚では、本人の意思を確認すること(例えば、ご質問のケースだと夫の意思の確認)が大切だということです。だから、公証人の本音を言えば、離婚の公正証書を作るときには、ご本人達を連れて来て欲しいのです。
では、離婚の公正証書の作成では、誰が代理人となれるのでしょうか? これは、各公証人の判断で決めていて、統一的なものがなく、公証人それぞれで違うこともあるのですが(公証人によってバラバラということ)、弁護士さんの場合には代理人となることを認めているようです。弁護士さんは、法律上の争いについて代理人として解決することができる立場にありますから。 行政書士などその他の士業についても、誠実に依頼を処理する義務がありますから、代理人として認めてくれることが多いです。 以上に対して、例えば、妻の実のお姉さんとなると、妻寄りの人で、信頼性に欠けるので、代理人としては認められないと思います。 (以上の記述は、普段お世話になっている、都心にある公証役場の公証人のお話を基にして書きました。)
離婚の公正証書を代理人によって作るのであれば、弁護士・行政書士などの士業に依頼した方がいいですね。 因みに、私は、代理人を認める公証人を存じ上げていますから、そのを参考にして公正証書の作成をしております。 |

【公正証書の内容のご相談】 離婚した後に、夫が所有する家を借りようと思います。理由は、お子さん達を、今と同じ学校に通学させたいので。 夫は、「家賃は安くするので、それが養育費代わりだ。」と言っています。離婚の時には、公正証書を作ろうと思いますが、夫の言うことに従って、安い家賃を養育費代わりとし、養育費の支払いについては決めなくてもいいのでしょうか? |
|
家の貸し借りの約束とは別に、「養育費を月〇万円支払う。」という約束(契約)を、公正証書で決めておいた方がいいですね。
具体的に考えて見ましょう。 仮に、相場からすると、その家の家賃が15万円とします。ご主人としては、家賃は5万円として、差額の10万円は養育費代わりというお気持ちとしましょう。 この家を貸すという約束が守られている間はいいのでしょうが、問題は、約束が守られなくなったときです。奥さんが家から出て行くときには、養育費に関する約束がないことになってしまいます。
結論としては、この場合は、ご主人は、養育費を10万円支払う、他方、奥さんは、家賃として15万円支払う、と言う約束をしておくべきです。 養育費代わりに家賃を安くする場合と、実質的には同じなのですが、このような約束にして、かつ、公正証書を作成しておけば、仮に、奥さんが家から出ることになっても、10万円の養育費の支払いについては、公正証書があり、万一、ご主人の養育費の支払いが滞っても、強制執行できる可能性を残すことができからです。 |

公正証書を作りたいと思っていますが、合意内容をまとめた原案の作成だけをお願いすることもできますか? |
|
はい、公正証書の原案の作成だけでもさせていただきます。 公証人や公証役場の職員とのやり取りはご自分でして頂きますが、多少お時間に余裕のある方であれば大丈夫だろうと思います。 お仕事等でお忙しい方であれば、公証役場とのやり取りもご依頼頂いた方が、効率的な公正証書の作成ができると思います。 |

公正証書で強制執行するためには「送達」が必要だそうですが、「送達」とは何ですか? |
|
「送達」についてのご質問ですが、難しい点もありますので、ザックリとご説明します。
例えば、離婚のときに公正証書を作って、養育費の支払いの約束をしましたが、万一、養育費の支払が滞って、強制執行が必要になったときには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を養育費を支払う方(ご主人のことが多いですね)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
|

離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか? |
|
公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。 |

離婚で公正証書を作って、不動産の財産分与についての約束もしようと思います。公正証書の作成のサポートだけではなく、不動産の登記について、司法書士さんのご紹介などをお願いすることもできますか? |
|
司法書士さんのご紹介についても、よくご質問があり、ご希望であれば、ご紹介をしております。 具体的に言うと、お付き合いのある司法書士さんに、事案の内容をご説明し、見積をいただき、登記に必要な書類を取り次ぎ、依頼者を司法書士さんに引き合わせる等のお手伝いをしております。また、公正証書の作成と登記の申請では、必要な書類が少し異なりますから、必要であれば、書類を代理人として取得することもいたします。 司法書士さんをご存知ない方がほとんどですから、司法書士さんを探し、見積をもらい、依頼する司法書士さんを決めるのは、少し面倒かも知れません。その辺のサポートもしておりますので、あまりご負担を掛けずに登記も済ませることができると思います。 |

離婚の際に公正証書を作成したいと思いますが、不動産が財産分与の対象となり、住宅ローンもあります。税金も問題となりそうなので、税務署へ相談に行ったら、税理士さんに相談した方が良いとアドバイスをもらいました。 公正証書のご依頼をする際に、税理士さんをご紹介いただくことも可能でしょうか? |
|
税金の問題は嫌ですよね。 一般的に言って、離婚でも税金が問題となることはありますし、中でも、住宅ローン付きの不動産は税金の注意が必要なようです。 税理士さんについては、親しい税理士さんをご紹介できます。そして、税理士さんと連携して問題に対応しますので、ご安心ください。 |

相続・遺言について
|

【あるメール相談から】 年金で細々と生活していて、銀行口座は夫が700万円、妻が600万円ですが、それぞれが先に亡くなった場合に備えて、遺言を作成しようか考えています。 相続税も課税されない、このような金額の相続の場合、遺言は不要でしょうか? |
|
遺言がないときには、民法が定める相続(法定相続)となります。つまり、民法には、夫や妻が亡くなった場合の相続人とその相続分が規定されていますが、遺言がないときには、その民法の定めに従った相続となります。 それに対し、遺言を作成することによって、民法の定める相続とは異なる、遺言者が希望する相続を実現することができます。 従って、「どのような相続を実現したいのか」という観点から、遺言の必要性をお考え下さい。
相続税の問題は、以上とは別の問題です。 |

遺言には、色々な種類(方式)のものがあるようですが、どのような遺言があるのか、概略を教えてください。 |
|
そうですね、遺言にも色々な種類(方式)があり、大きく分けると、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」に分かれます。 「普通方式の遺言」には、自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言があります。それに対して、「特別方式の遺言」には、一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、そして在船者遺言があります。
「特別方式の遺言」は、どれも特殊な遺言ですから、通常は、お考えになる必要はありません。そして、「普通方式の遺言」のうちでも、遺言として良く使われるのは、「ご自分で作る自筆証書遺言」と「公証人に依頼して、公正証書で作る公正証書遺言」です。 遺言の作成をお考えでしたら、自筆証書遺言と公正証書遺言をお調べになられて、どちらがご自分の状況、遺言内容などに適しているのかをお考え下さい。 |

自分で遺言を書こうと思いますが、遺言を作る上で、絶対に守らなければいけないことを、教えてください。 |
|
「ご自分で遺言を書こう」となさっているのですから、自筆証書遺言をお作りになろうとしているのですね。でしたら、以下の点を守って、遺言を作ってください。
1 遺言書の全文、日付、氏名を、ご自分で書いてください。 ただし、近年の法律改正で、「ご自分で書く」という要件が少し緩和されて、相続財産の特定に必要な事項(つまり財産目録)は、パソコンによる記載や登記事項証明書・預金通帳のコピーを添付する方法でも良いとされました。
2 日付は、例えば、「令和4年8月1日」というように、作成年月日が明確になるように書いてください。
3 氏名は、本名(戸籍上の氏名)を書いてください。そして、氏名の後に押印してください。印鑑は、実印でも、認印でも大丈夫です。 なお、ご住所を書く必要はありません。 |

遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。 特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか? |
|
遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。 遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。
この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。 両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。 |

遺言を作って、特定の財産(銀行預金など)をお世話になった方に遺贈したいと思っていますが、遺贈を受ける方は、財産をもらわないとすることもできるのでしょうか? |
|
特定の財産を遺贈しようという場合ですから、これは特定遺贈ですね。特定遺贈では、遺言を作った方が亡くなった後は、遺贈を受ける方は、いつでも遺贈を放棄(遺贈を受けないという意思表示)することができます。遺贈を受ける方の意思を尊重しようとしているのですね。
なお、義務も一緒に遺贈の対象となっている包括遺贈の場合(例えば、内縁の配偶者に全財産を包括遺贈する等のケース)には、遺贈を受ける方は「相続人と同じ立場に立つ」とされていますので、遺贈の放棄は、自己に対する遺贈があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 |

遺贈(遺言で財産を贈ること)をしようと思いますが、遺言者(遺言を作った方)よりも先に、受遺者(遺贈を受ける方)が亡くなったときは、遺贈はどうなりますか? |
|
遺言者よりも受遺者が先に亡くなったときは、遺贈は効力を生じません。亡くなった受遺者の相続人が、当然に、新たな受遺者になることはなく、受遺者が受けるべきであった財産は、相続人が相続することになります。 もし、遺言者よりも先に受遺者が亡くなったときには、亡くなった受遺者のお子さんに遺贈したい等のご希望があれば、その旨を遺言に記載しておく必要があります。これは予備的にしておく遺贈ですから、「予備的遺贈」と言います。 |

予備的遺言というものがあるそうですが、予備的遺言とは、どのようなものですか? |
|
予備的遺言とは、補充遺言とも言いますが、以下のようなものを言います。
例えば、奥さんとお子さんが二人いるAさんが、遺言を作ろうとしたとします。 その場合、通常は、奥さんとお子さん二人に、どの財産を相続させるかを遺言に記載することになりますね。しかし、もしかしたら、奥さんはAさんが亡くなる以前に亡くなるかも知れません。そこで、その場合に備えて(予備的に)、奥さんが先に亡くなったときには、「奥さんに相続させるつもりであった財産をどうするか」も記載しておくことが出来ます。これを、予備的遺言と言います。
実際の遺言作成では、良く使われます。 |

遺言には、「付言」というものがあるそうですが、どのようなものですか? |
|
多くの遺言でそうだと思いますが、その遺言を作った理由、遺言のように財産を分けた理由があるはずです。また、家族に対する感謝の気持ち、遺言者が居なくなった後の家族への希望(仲良く、穏やかに暮らして欲しい等)などもあるかと思います。 これらのことも、遺言に記載しておくことができ、これを、「付言」と言います。 「付言」というのは、聞き慣れないでしょうが、実際の遺言では、良く(非常によく?)使われています。 |

公正証書で遺言を作るときには、証人が必要なのでしょうか? |
|
公正証書で遺言を作る時には、証人が2人以上必要とされていて(民法969条1項)、通常、公証役場では、2人の証人の立ち会いのもとで公正証書遺言を作っています。 なお、この証人も、公正証書に署名・捺印をします。 |

公正証書で遺言を作るときに必要とされる証人は、誰でもなれるのでしょうか? |
|
公正証書で遺言を作るときの証人には、相続人となることが予想される方(推定相続人)、遺言で財産をもらう方(受遺者)、未成年者等はなることが出来ません(民法974条)。 |

遺言を公正証書で作ろうと思うのですが、必要とされる証人2人を揃えることができずに困っています。 このようなときは、どうすればいいのでしょうか? |
|
公正証書で遺言を作るときには証人2人が必要ですが、相続人となることが予想される方(推定相続人)、遺言で財産をもらう方(受遺者)などは証人にはなれません。また、証人をお願いすると、遺言の内容を知ってしまいますから、証人をお願いするのに相応しい方は少ないかも知れません。 そのようなときは、公証役場にお願いすれば、法務局のOBを証人として用意してもらえます。お礼は必要ですが、おそらく二度と会うことはありませんから、気持ちは楽だと思います。
なお、私が公正証書遺言の作成をお手伝いするときには、私も証人を務めさせていただきますし、もう1人の証人として、仲間の行政書士をお連れすることも出来ます(その方へのお礼は必要ですが)。 |

遺言には、遺言執行者も書くと聞きましたが、遺言執行者とは、何ですか? |
|
遺言者が亡くなった後に、遺言内容を実現することを、「遺言の執行」と言いますが、この「遺言の執行」をする方を遺言執行者と言います。 |

遺言には、遺言執行者を決めておくべきなのでしょうか? |
|
遺言執行者を決めなければいけないということはありません。 その上で、遺言執行者を決めておくか否かですが、遺言を公正証書で作る場合には、遺言執行者を記載します。他方、ご自分で書く遺言(自筆証書遺言)では、ケースバイケースかと思います。
当たり前ですが、遺言は作成するだけでは意味がなく、その遺言内容を実現する必要があります。しかし、不満のある相続人が居る等の理由で、遺言が迅速に実現されないことがあります。そこで、遺言執行者を指定しておき、遺言内容の迅速な実現に務めるのです。実際の相続手続では、遺言執行者の実印だけで手続きを済ませることも可能で(相続人の実印は不要)、遺言執行者を指定しておく意味はとても大きいです。 従って、遺言内容の実現のために、遺言執行者を定めておいた方がいいか否か、それをお考えになって、遺言に遺言執行者を記載するか否かをお決めください。 |

遺贈では、遺言執行者を決めておいた方がいいのでしょうか? |
|
遺贈とは、遺言で財産を贈ることを言います。 例えば、内縁の奥さんが居る場合に、財産を、相続人である兄弟にではなく、遺言で内縁の奥さんへ贈ることがそうです。 この場合、遺言内容を実現するために、銀行などの手続きが必要ですが、遺言執行者の指定がなければ、相続人がその手続きをする必要があります。しかし、どうでしょうか・・・相続人である兄弟は、それを喜んでするでしょうか。面白くない相続人も居るかも知れませんから、内縁の奥さんを遺言執行者として、遺言内容を確実に実現させる方がいいですね。 従って、遺贈する場合には、その遺贈を受ける方を遺言執行者としておくことがいいです。 |

誰を、遺言執行者とすればいいのでしょうか? |
|
遺言執行者には、未成年者や破産者はなれないという制限がありますが、その他には制限はありません。従って、相続人でも、遺言で財産をもらう受遺者でも遺言執行者となることができます。 そもそも、遺言執行者を決める目的は、遺言の内容を確実に実現するためですから、基本的には、遺言で財産をもらう方を遺言執行者とすることが良いと思います・・・その方は、一生懸命、遺言を実現するでしょうから。 ただ、遺言の内容が複雑だったりして、相続人や受遺者には負担が大きいときには、行政書士、弁護士などのプロにお願いするのが良いと思います。 |


父が亡くなり、遺言があります。封がしてあり、遺言の内容は分からないのですが、こういう段階から相談しても良いですか? |
|
はい、大丈夫です。 遺言を開ける手続きを裁判所でする必要がありますし、並行して戸籍を集める必要もあります。これからの手続きの流れなどもご説明いたします。 |


亡くなった父が書いた遺言が、出てきました。封がしてあり、勝手に開けてはいけないと聞きました。 どうしたら良いでしょうか? |
|
| お父様がお書きになった封をされた遺言は、勝手に開けることはできません。家庭裁判所で検認という手続きで開けます。そこで、家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。 検認をしていないと、登記所・銀行等の手続きで使えませんので、ご注意ください。 |


| 公正証書の遺言があります。公正証書の遺言も、家庭裁判所へ持って行く必要があるのでしょうか? | |
| 公正証書の遺言には、検認などの裁判所の手続きは必要ありません。公証人が作成した遺言で信頼性が高いということです。 遺言が公正証書で作成されていると、家庭裁判所の検認が必要ないので、相続人としては、とても助かります。 |


| 母が亡くなり、色々な書類が出てきました。ご相談に伺うのに、どれを持って行ったらいいのか分かりません。 | |
| そうですね。多くの、見たこともない書類があるかも知れません。私が伺って、書類を見せて頂くこともできます。どうするか、ご相談しましょう。 |


| 相続人は兄弟3人ですが、行政書士さんに依頼するには、私1人からの依頼で良いでしょうか? | |
| 相続人のうちのお1人からの依頼で良いですし、むしろ、そうすべき場合もあります。 |


| 母が亡くなり、相続人は兄弟2人です。遺産分割は、話し合いで穏便に済ませたいと希望しています。ただ、もめる可能性もあり、その時は、家庭裁判所で調停をしようと思っています。このような事案でも、ご相談に乗っていただけますか? | |
| はい、ご相談にお乗りし、お手伝いをさせていただきます。 もめるか否かは、現時点では分からないことですから、相続財産の確認などの手続きを進め、もし、先々、もめたら家庭裁判所の調停で話し合って頂くことにしましょう。 |


戸籍集めは、思った以上に手間が掛かることが分かりました。 戸籍を集めてもらうこともできますか? |
|
はい、戸籍を集め、相続人を確認することもいたします。 亡くなった方の出生まだ遡ると、戸籍の数が増えますし、古い戸籍は字が読みにくいだけではなく、複雑なことも少なくありませんから、戸籍集めで行き詰ったらご相談ください。 相続人を確認した後は、相続関係説明図という相続関係を明らかにする書面もお作りいたします。銀行等の手続きで、使っていただける書面です。 |


遺言がありますが、遺言と異なる遺産分割はできますか? |
|
| 相続人全員が合意なされば、遺言と異なる遺産分割ができます。 |


| 母が亡くなり、相続人は私1人だけですが、仕事が忙しくて、あまり時間がありません。母の相続を全てお願いすることはできますか? | |
| そのようなご依頼もお受けできます。ただ、中には相続人でなければできない手続きがあるかも知れません。そのときには、ご負担がなるべき軽くなるように工夫いたしますので、ご相談させてください。 |
離婚や公正証書でお悩みがありましたら、ぜひ瓜生行政法務事務所までご相談くださいませ。