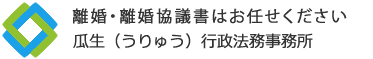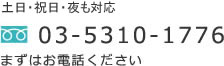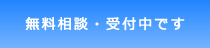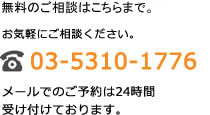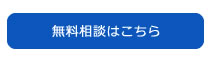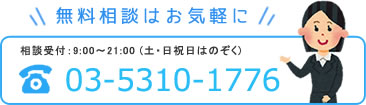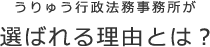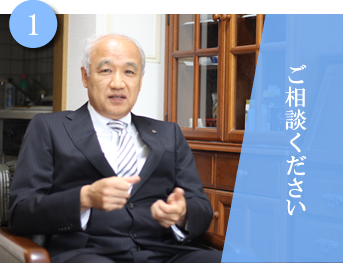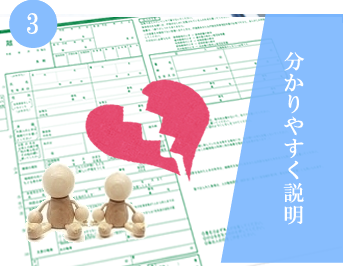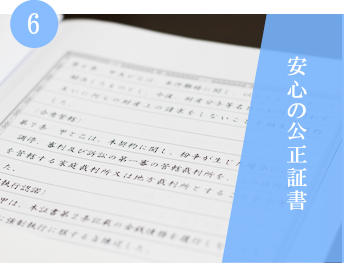【遺言と公正証書】 遺言を公正証書で作る理由とは?
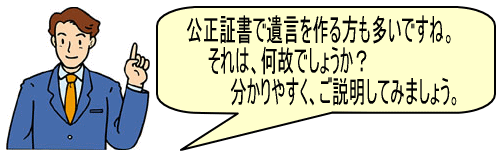
1.公正証書による遺言は増えている。
公証人からお聞きしたお話しでは、「公正証書の作成では、遺言と離婚が多い。」そうです。
統計によっても、日本公証人連合会によれば、平成29年の遺言公正証書の作成件数は11万件を超え、10年前の約1.5倍となっています。
遺言については、出版物やテレビなどのマスコミで取り上げられることも多くなっています。そのような事情もあり、遺言への関心が高いのかと思います。
また、ある調査によれば、50歳代から相続への関心が高まり、その背景には、自らの健康不安のほか、親や親戚の資産を相続した際にトラブルを経験したことがあるそうです。

もともと、遺言を作成する方には、遺言により実現したい目的があるはずです。
■法律で定める相続とは異なる相続を実現したい(例えば、お子さんのいないご夫婦で、全ての財産を奥さんに相続させたい等々)
■遺言によって、自らの気持ちを明確にして、相続争いを未然に防止したい
■遺言によって、円滑な相続手続きを実現したい 等々・・・
これらの目的を実現するための配慮がなされた遺言を作成することにより、目的が実現される可能性が高まってきます。
そして、遺言を作成するときに、公正証書が利用されることが多いです。公正証書による遺言が使われる理由としては、次の点を挙げることが出来ます。
Ⅰ確実な遺言が作れる
Ⅱ紛失や、偽造・変造の恐れがない
Ⅲ証明力が高い
Ⅳ検認が不要である
Ⅴご高齢で体力が弱くなってきたり、ご病気でも作成できる
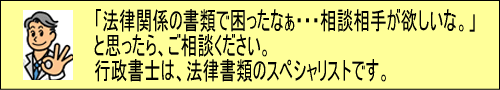
2.公正証書による遺言が使われる理由
公正証書による遺言が使われる理由を、少し詳しく見ていきましょう。
【公正証書で、確実な遺言が作れる】
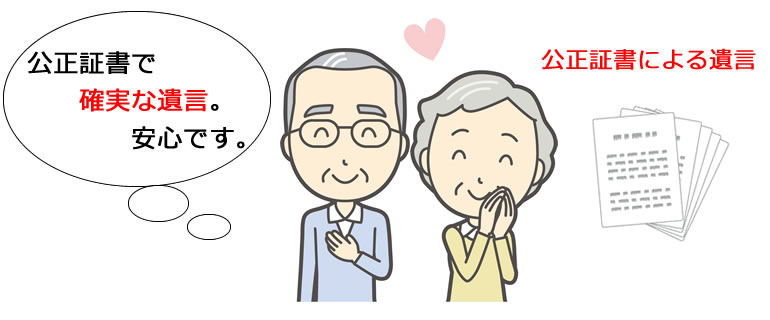
遺言者が自分だけで作成する自筆証書遺言と比較して、「公正証書による遺言は、確実な遺言だ。」と言われます。
自筆証書遺言の場合には、ご自分自身で法律で定められた方式に従って作成しなければならないですし、また、訂正方法も法律で定められている。これらに反すれば、遺言の全てまたは一部が法律的に効力がない恐れがあります。さらに、内容としても、法律的には意味の無いことが記載される恐れもあります。
それに対して、公正証書による遺言の場合には、裁判官・検察官等の経験者で法律の専門家である公証人が作成しますから、形式・内容について、法律的に効力がない可能性は極めて低く、そのために、確実な遺言と言われるのです。
遺言は、どの遺言もその内容が実現される必要がありますが、
・遺言で、法律で定める相続とは異なる相続を実現したい場合(お子さんのいないご夫婦で、全ての財産を奥さんに相続させたいケース、内縁・事実婚でそのパートナーに財産を渡したいケース等)
・特定の相続人に多くの財産を相続させたい場合
・財産が多い場合
・相続人が多い場合 などには、特に遺言が確実に実現される必要があり、公正証書遺言が確実な手段となるでしょう。
【公正証書遺言には、紛失や、偽造・変造の恐れがない】
遺言者がご自分で作成する自筆証書遺言には、紛失の恐れや、偽造されたり、変造されたりする可能性があります。
しかし、公正証書遺言を作成した場合には、遺言者には、作成の当日に、正本と謄本が渡されますが、原本は公証役場が保管しますので、紛失・偽造・変造の恐れはありません。
【公正証書遺言は、証明力が高い】
自筆証書遺言の場合には、本人の遺言なのかと疑問が出ることがあるかも知れません。特に、遺言の内容に不満があれば、なおさらでしょう。
それに対して、もともと、公正証書は証明力が高い書類ですが、遺言の場合も証明力の高さは同じです。即ち、公証人という第三者が法律の専門家という立場で、遺言者の意思を確認して作成し、証人も公正証書遺言の作成に立ち会うのですから、本人の遺言であることは確実です。
【公正証書遺言は、検認が不要である】

公正証書遺言について、民法1004条は、家庭裁判所による検認は不要である旨を定めています。知る人ぞ知る、公正証書遺言の大きなメリットです。「遺言を公正証書で作る最大のメリット」と言われることもあります。
例えば、自筆の遺言書であれば、家庭裁判所による検認の手続きが必要になります。検認について、民法1004条は、「遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」と定めています。自筆証書遺言は、この定めに従うのです。
この遺言の検認は、遺言が存在することを確認して、保存を確実にするための手続きであり、遺言が偽造・変造されることを防止するための措置です。検認が済むと、家庭裁判所は、検認が済んでいるという証明書を付けてくれます。
この家庭裁判所に検認を申し立てるためには、遺言者の戸籍を出生まで遡って集める必要がありますから手間と時間が必要ですし、家庭裁判所に申し立てた後、検認までは時間が掛かります。また、検認は、遺言の有効・無効とは関係がないのですが、銀行の手続きや不動産の登記等は、検認が済んでいないと、受け付けてもらえません。検認を済ませないと、相続手続きが進まないということになります。
公正証書遺言であれば、この家庭裁判所による検認は不要ですので、手間と時間を省くことができ、迅速な相続手続きが可能になります。
【体力がなくなってきたり、ご病気でも作成ができる】
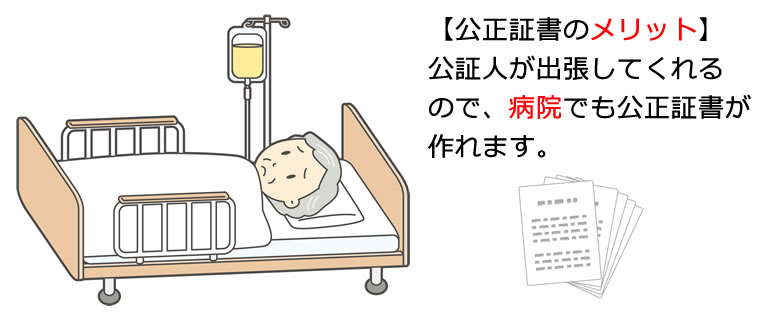
ご自分で作成する自筆証書遺言では、全文を自分で自書する必要がありますから、ご高齢で体力が弱くなってきたり、病気が重くなってなってきたときには、その作成が難しいこともあるかと思います。
しかし、公正証書による遺言の場合には、遺言の内容が決まっていれば、後は、公証人が、法律の定めに従って作成しますので、遺言の作成が可能です。
なお、お願いすれば、公証人は、ご自宅や病院等にも出張してくれますので、公証役場に行けなくても公正証書遺言の作成は可能です。
以上のように、公正証書遺言には、大きな長所があります。作成のための手数料がかかったり、公証人に提出する資料をあつめる、公証役場とのやり取り等の手間もかかりますが、それぞれの方のご事情に応じて、遺言を公正証書で作成するか否かをお考えください。
また、遺言内容の迅速で、確実な実現のためには、遺言執行者(遺言の内容を実現するための手続きをする人)を遺言で指定して、遺言の実現を任せることもお考えになると良いと思います。
3.行政書士による公正証書の作成サポート
行政書士は、遺言の内容についてのご相談から、原案の作成、必要な資料の収集、公証人との打ち合わせ、作成の依頼などの公証役場とのやり取りまで、お手伝いをさせていただきます。体力的に自信がない、仕事が忙しい等の理由により、遺言作成のお手伝いを必要とされるときには、お気軽に、お電話でのご相談からお始めください。
[公正証書作成・ご相談・サポートコース]
公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。
基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。
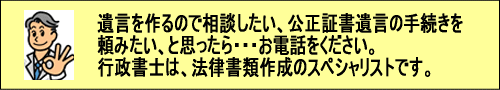

公証役場 紹介
今回、ご紹介するのは、東京都千代田区にある丸の内公証役場です。
【丸の内公証役場】 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 電話 03(3211)2645
丸の内公証役場のホームページ 詳細はこちら >>
時々、都心の公証役場を利用するのですが、先日、初めて丸の内公証役場を利用しました。千代田区丸の内と言えば、有名なオフィース街ですが、あまり馴染みはなく、行き方もネットで検索する始末でした。
JR有楽町駅の国際フォーラム口から出て、国際フォーラムに沿って左に、1つ目の角を右へ、そのまま直進すると「新東京ビル」があります。JR有楽町駅から、徒歩4~5分で到着です。
そのビルの2階に、丸の内公証役場があります。
新東京ビルの2階に上がると、落ち着いた雰囲気の廊下。事務所や会社が並んでいました。

そして、丸の内公証役場は、235区にありました。

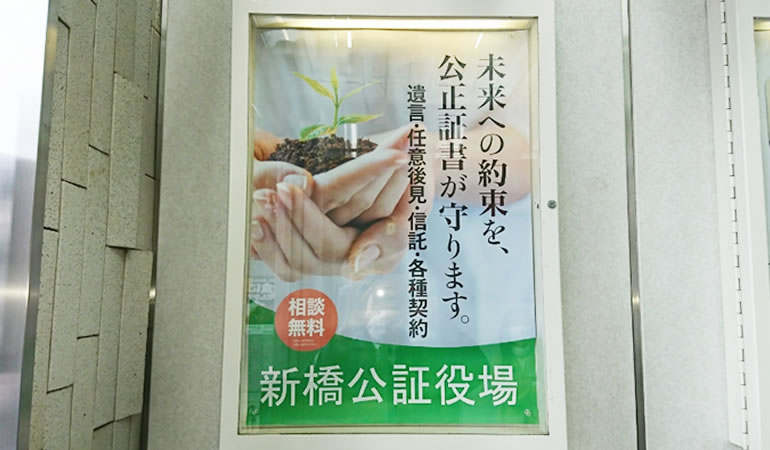
(公証役場へ行くと良く見かけるポスターです。「未来への約束を、公正証書が守ります。 遺言・任意後見・信託・各種契約」という言葉は、公正証書が果たす役割り・機能を言い表しています。新橋公証役場にて)
ページ名 「遺言と公正証書 遺言を公正証書で作る理由とは?公正証書の作成サポートはお任せください。」
文責 行政書士による公正証書作成サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
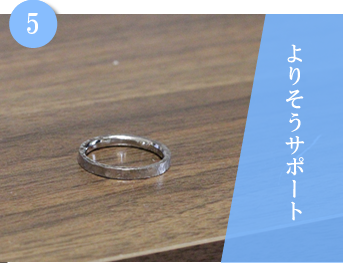
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。

よくある質問 相談について
公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
【あるメール相談から】 年金で細々と生活していて、銀行口座は夫が700万円、妻が600万円ですが、それぞれが先に亡くなった場合に備えて、遺言を作成しようか考えています。 相続税も課税されない、このような金額の相続の場合、遺言は不要でしょうか? |
|
遺言がないときには、民法が定める相続(法定相続)となります。つまり、民法には、夫や妻が亡くなった場合の相続人とその相続分が規定されていますが、遺言がないときには、その民法の定めに従った相続となります。 それに対し、遺言を作成することによって、民法の定める相続とは異なる、遺言者が希望する相続を実現することができます。 従って、「どのような相続を実現したいのか」という観点から、遺言の必要性をお考え下さい。
相続税の問題は、以上とは別の問題です。 |


遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。 特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか? |
|
遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。 遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。
この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。 両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。 |


遺言を公正証書で作ろうと思うのですが、必要とされる証人2人を揃えることができずに困っています。 このようなときは、どうすればいいのでしょうか? |
|
公正証書で遺言を作るときには証人2人が必要ですが、相続人となることが予想される方(推定相続人)、遺言で財産をもらう方(受遺者)などは証人にはなれません。また、証人をお願いすると、遺言の内容を知ってしまいますから、証人をお願いするのに相応しい方は少ないかも知れません。 そのようなときは、公証役場にお願いすれば、法務局のOBを証人として用意してもらえます。お礼は必要ですが、おそらく二度と会うことはありませんから、気持ちは楽だと思います。
なお、私が公正証書遺言の作成をお手伝いするときには、私も証人を務めさせていただきますし、もう1人の証人として、仲間の行政書士をお連れすることも出来ます(その方へのお礼は必要ですが)。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。