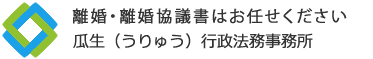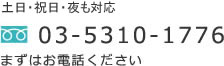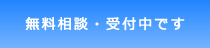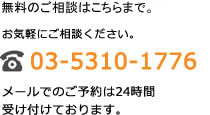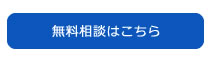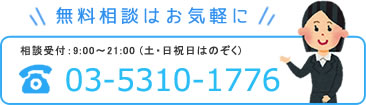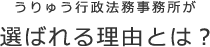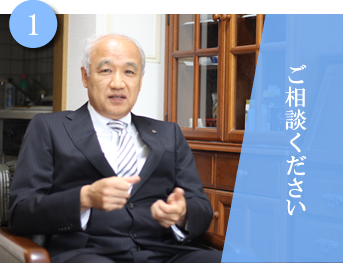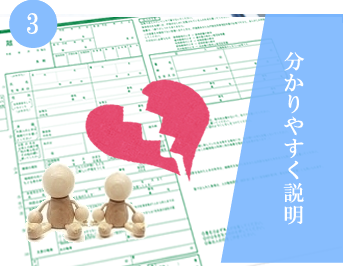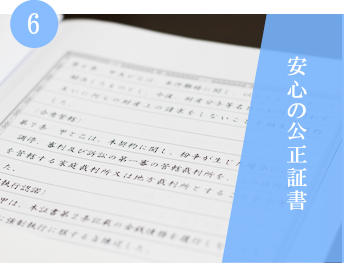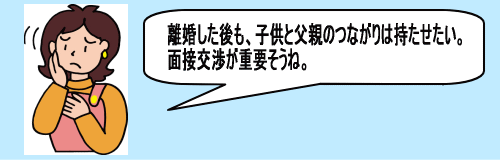
1.簡単な具体例でご説明
面接交渉または面会交流と言われても、なかなかイメージは出来ないかも知れません。そこで、まず、簡単な具体例を考えて見てください。
信彦さん・恵子さんご夫婦は、話し合って離婚することになりました。お二人には、お子さんの直樹ちゃんがいます。親権者については、信彦さんが直樹ちゃんに会えることを条件にして、恵子さんが親権者となり、恵子さんと直樹ちゃんが一緒に暮らすことになりました。
この様に、お子さんと一緒に暮らさなくなった他方の親がお子さんに会うことについては、どのように決めておけば良いのでしょうか?

離婚によってお子さんと一緒に暮らさなくなった他方の親が、子供と会い・一緒に過ごしたり、または、電話や手紙などの方法で子供と接触することを、面接交渉または面会交流と言います。
具体例でも、信彦さんと恵子さんは、面接交渉(面会交流)について、話し合い、合意して、決めておくことが多いです。
面接交渉(面会交流)は、離婚協議書や離婚の際の公正証書に記載しておく典型事項と言えるでしょう。
なお、従来は、「面接交渉」という言葉が使われるのが一般的でしたが、平成23年に民法766条が改正されて、「面会及びその他の交流」という表現が明文化され、「面会交流」という言葉が多く使われるようになってきました。そこで、このホームページでも、「面接交渉または面会交流」「面接交渉(面会交流)」という表現を使うことにしました。
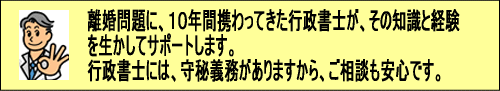
2.面接交渉(面会交流)の決め方
面接交渉(面会交流)の考え方や決め方についても、なかなか難しい問題があります。以下では、私の経験も踏まえてご説明させていただきます。
面接交渉(面会交流)をどのようにするかについては、協議離婚の場合であれば、ご夫婦の話し合いで決めることができます。
面接交渉(面会交流)には、お子さんに会うことのほかにも、電話などの様々な内容が含まれていますが、やはり重要なのはお子さんに会うことです。
ですから、お子さんに会うことについて、ご夫婦間で取り決めておくことが多くなります。
では、それを、どの程度具体的に決めておくのでしょうか?
ご夫婦間では、「必ず月1回会わせる。」「月2回会わせる。」などの話しが出てくるかも知れません。さらに、より詳細な定め方として、「毎月第1日曜日午後1時から午後5時」などの決め方も離婚に関する本では書かれていることもあります。
しかし、あまり具体的な、明確な決め方をすると、「面接交渉が硬直化し、余裕をもって行われない弊害を招きやすい」という指摘もあります。
面接交渉(面会交流)を考えるとき、もっとも大切なのは、お子さんの福祉であり、お子さんの生活状況・情緒面への配慮、また、お子さんと一緒に暮らしている母親(または父親)の養育の内容との調和等を考慮します。
そのような観点からは、お子さんの状況を考えながら、柔軟な面接交渉(面会交流)ができるように、面接交渉(面会交流)については、例えば、「その時の状況に応じて連絡を取りながら行っていきましょう。」というように、包括的な決め方をすることが望ましいとされています。
また、例えば、回数を決める場合でも、「月1回」と明確には決めず、「月1回程度」というように、幅を持たせる決め方が良いと指摘されています。
以上に述べたことは、家庭裁判所における離婚調停等においても、基本的に同様の考え方です。また、協議離婚の際の約束を公正証書にする場合であれば、公証人も同様の考え方をしていることが多いでしょう。公証人は、家庭裁判所の動向には敏感です。
そういう点から言えば、公正証書で面接交渉について決める場合には、包括的・抽象的な決め方になることが多く、詳しく・具体的な決め方をすることは、なかなか難しいだろうと言えると思います。
3.ご夫婦の色々なご希望
ただ、ご夫婦間では、面接交渉(面会交流)について、色々なご希望が出てくることがあります。
宿泊を伴う面接、運動会等の学校行事への参加等々です。
公証人とお話しをして、これらのことを具体的に決めることは、なかなか難しいでしょう。離婚せざるをえなくなったご夫婦が、連絡を取って、これらのことを行っていくことには、かなりの困難があると指摘されています。
ご参考までに書くと、面接交渉(面会交流)は連絡を取りながら行って行きましょうと決めて、将来の検討課題として、宿泊を伴う面接、学校行事への参加等があることを確認しておくという方法もあります。公証人の中には、この様な決め方を認めてた方もいらっしゃいます。
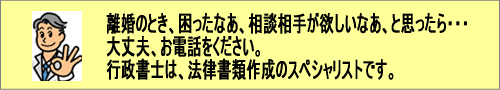

ページ名 「面会交流・面接交渉とは?どのように決めるの? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
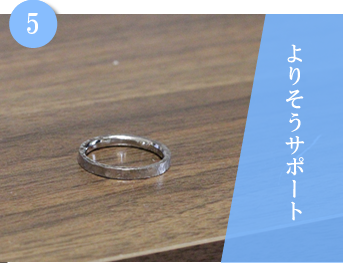
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
|
お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |


離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |
|
公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |


養育費については、公正証書を作るメリットが大きいと聞きましたが、どういうことでしょうか? |
|
養育費を払ってもらうための強制執行では、特例が認められています。 例えば、会社員である元の夫が、養育費の支払いを怠ったときには、元の妻は、毎月の養育費のために、元の夫の将来の給料も差押えることができ、将来の養育費も給料から天引きで受け取ることが出来ます・・・別の言い方をすると、「元の妻は、毎月裁判所に申し立てをしなくても、給料日ごとに元の夫の勤務先から、養育費に相当する金銭を支払ってもらえる」のです。
強制執行では、「既に未払いになっている金銭を支払ってもらう」のが原則ですから、将来の養育費も、元の夫の先々の給料からもらえるというのは大きなメリットです。これは、養育費がお子さんの日々の生活を支えるために必要な金銭であることから認められました。 |
ご相談ならぜひお問合せくださいませ。