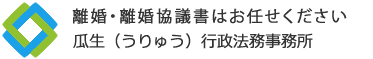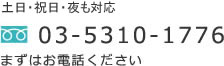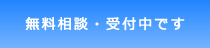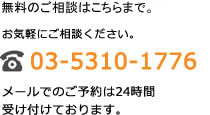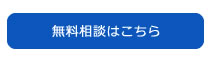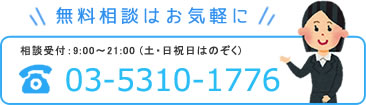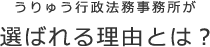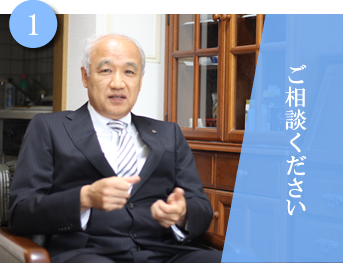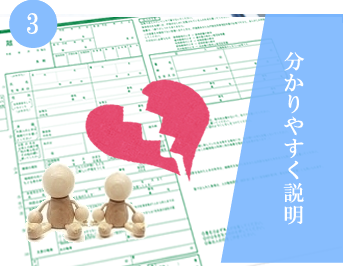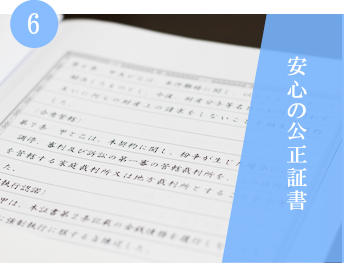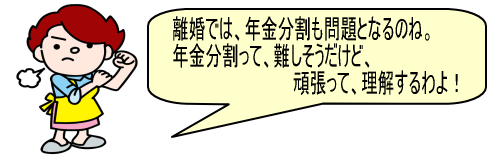
1.年金分割 初めに
年金分割が平成19年に始まった時には、どちらかというと、年金分割は熟年夫婦のためのものという印象を受けました。しかし、現在では、婚姻期間の長い・短いを問わず、離婚の際には年金分割が問題になることが多いのです。年金というと難しそう、というイメージがありますが、出来るだけ簡潔に説明してみようと思います。最後までお読み頂けたら、と思います。
2.年金分割とは、どういうことでしょうか?
例えば、夫が会社員で厚生年金に加入している場合には、毎月その保険料を納めていて、その記録が残されています。年金分割とは、婚姻期間中の夫の保険料納付についての記録の一部を、妻の年金の記録に移すことを言うのです。その結果として、受け取る年金額が増えるのです。
この年金分割を理解するためには、年金制度を理解する必要があります。年金制度は、①「国民年金」を1階部分、②厚生年金・共済年金という「被用者年金」を2階部分、③「企業年金」を3階部分とする3階建ての構造となっています。
年金分割は、この2階部分の厚生年金と共済年金を分割する制度なのです。
良くある誤解として、離婚した場合、夫の年金(例えば、年間240万円)の最大で半分(年間120万円)を、妻が受け取ることになるのではないか、というものがあります。
しかし、年金分割は、厚生年金・共済年金について婚姻期間中の保険料納付についての記録を分割する制度であって、上記のように夫の年金が半分になるということにはなりません。国民年金や企業年金は、分割の対象とはされていませんし、厚生年金・共済年金にしても、最大限、婚姻中の記録の半分が移るということです。この点は、誤解の無いようにしてください。
3.では、離婚時の年金分割という制度は、何故、作られたのでしょうか?
例えば、結婚して30年後に、離婚なさったご夫婦がいるとしましょう。ご主人は会社に勤め、厚生年金の保険料を納め、奥さんは専業主婦だったとします。
年金分割という制度がないと、ご主人は十分な年金を受け取れても、奥さんの年金は十分ではない、ということになります。ご主人の受け取る年金額と奥さんの受け取る年金額には、大きな差が生じるのです。このように、ご夫婦の片方が十分な年金を受け取れないという不都合を是正するために、年金分割という制度が作られました。
また、婚姻期間中のご主人の給料には奥さんの協力が認められます。その給料の一部が厚生年金の保険料として納められる以上、納めた保険料にも奥さんの協力を認めることができます。そこで、婚姻期間中に会社員であるご主人を支えた奥さんの協力を年金額に反映させる趣旨で、年金分割の制度が始まったのです。
4.年金分割の対象となる年金は?
年金にも色々な種類の年金がありますね・・・私も、詳しくはないのですが・・・
年金のなかでも、年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金だけです。民間のサラリーマンであれば厚生年金に加入していますし、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員であれば共済年金に加入しています。この厚生年金と共済年金が、年金分割の対象となります。
年金分割についての説明が長くなってきましたので、「年金分割の種類」と「年金分割の手続きのポイント」については、「年金分割 早分かり (2)」でご説明することにします。 → 「年金分割 早分かり (2)」へ
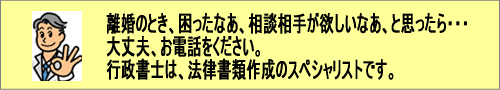

ページ名 「離婚時の年金分割 早わかり(1) 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
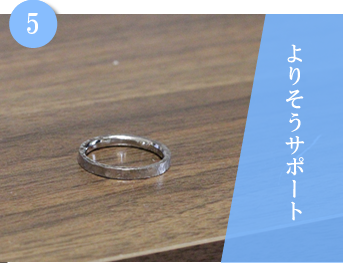
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |
|
お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |


離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
|
概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |


公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? また、公証役場での代理人をお願いできますか? |
|
代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。
公正証書を作成するための代理人もさせて頂きます。 公正証書を作るためにも法律的な専門知識が必要ですから、代理人も行政書士、弁護士などの専門知識を持った方にお願いした方が良いと思います。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。