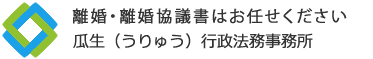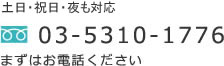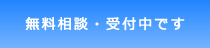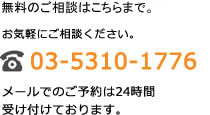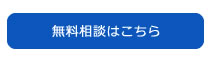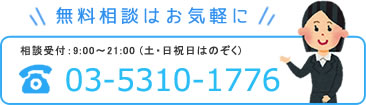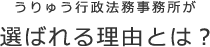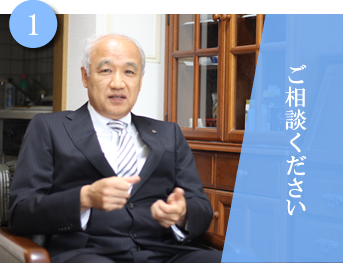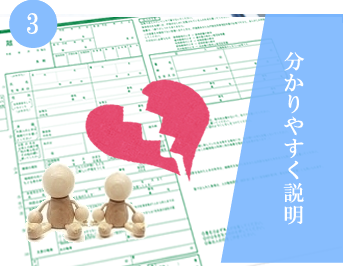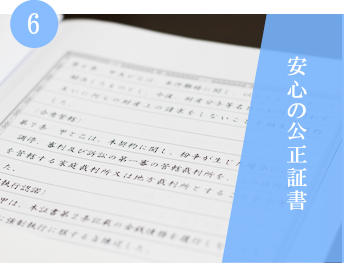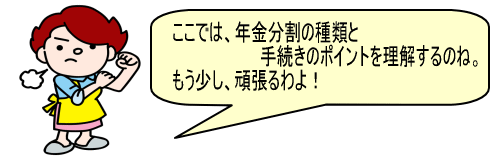
「離婚時の年金分割 早分かり (1)」では、年金分割とはどういうことなのか、年金分割という制度が作られた理由、年金分割の対象となる年金についてご説明しました。
このページでは、続きとして、年金分割の種類、年金分割の手続きのポイントについてご説明しましょう。
5.年金分割の種類
知られていないことも良くあるのですが、実は、年金分割には、①合意分割と②3号分割の2種類があります。
(1) 合意分割は、平成19年4月から始まりました。
合意分割とは、夫婦間で年金を分割することと、分割する割合を決めて年金を分割することを言います。
この合意分割をするためには、配偶者の一方が第3号被保険者(例えば、専業主婦)であった期間があることが必要とされています。
また、合意分割ができるのは、平成19年4月1日以降に成立した離婚ですが、年金分割の対象となるのは、平成19年4月1日以降だけではなく、婚姻期間の全体が年金分割の対象となります。
(2) 3号分割は、平成20年4月から始まりました。
3号分割は、平成20年4月以降に、配偶者の一方が第3号被保険者(例えば、専業主婦)であった期間があるときに、その期間について、他方配偶者(第2号被保険者:例えば、会社員)の保険料の納付記録の2分の1を自動的に分割できる制度です。
合意分割と異なり、夫婦間での合意は必要なく、第3号被保険者が請求すれば当然に分割されます。
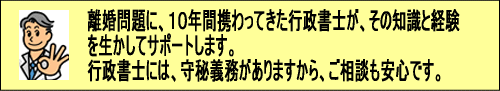
6.年金分割の手続きのポイント
離婚時の年金分割の手続きのポイントと、アドバイスをお話ししましょう。年金分割には、合意分割と3号分割がありますが、まずは、合意分割からです。
■合意分割
合意分割をする場合には、分割をする割合を決める必要があります。
ただ、「どういう割合で分割ができるか?」は、ご夫婦毎に違いがあります。そこで、年金事務所や共済組合等では、「年金分割のための情報通知書」という書類によって、そのご夫婦について、年金を分割できる割合を教えてくれます。まずは、「年金分割のための情報通知書」を年金事務所・共済組合等に請求しましょう。
そのうえで、「年金分割のための情報通知書」を参考にして、年金を分割する割合を決めます。この割合は、ご夫婦で話し合って決めることも出来ますし、もし、話し合いがまとまらない等の事情があれば、家庭裁判所の調停等を利用することも出来ます。
分割する割合が決まったら、次は、年金事務所等に対して年金分割の請求をすることになります。
この請求の方法には、協議離婚の場合には、大きく分けて2つの方法があると思ってください。
第1は、ご夫婦2人が揃って、年金事務所等に行って、手続きをする方法です。写真付の身分証明書によって、本人確認がされます。
第2は、公正証書で、分割する割合を定めて、手続きをする方法です。本人確認は、公証役場で、公正証書を作成する時にされています。
この2つの方法の違いは、公正証書により手続きをする場合には、ご夫婦の一方(主に、奥さんでしょう。)だけで、年金事務所等へ行って手続きをすることが出来ることです。これには、大きなメリットがあります。以下に、少し詳しく書きましょう。
年金分割の手続きをする時期は、離婚に伴う戸籍の手続きが終わり、新しい戸籍が出来た後になります(離婚していることを戸籍で証明する必要がありますから)。つまり、離婚届を提出してから、年金分割の手続きまで、間隔が空くことになるのです。離婚届を提出して、時間が経った後で、離婚したご夫婦が揃って年金事務所等に行くというのは、難しいこともあるかも知れません。だとすれば、養育費や財産分与等について公正証書を作成するのであれば、年金分割についても公正証書で定めておく方が、年金分割の手続きもしやすくなるでしょう。このような事情から、年金分割について、公正証書で定める場合も多いのです。
あと重要なことは、年金分割の手続きには、期間の制限があるということです。
家庭裁判所に調停の申し立てをしている等の場合は別ですが、原則として、年金事務所等での年金分割の手続きは、離婚してから2年以内(正確には、離婚した日の翌日から2年以内)にしなければなりません。
離婚するときには、離婚する前も、離婚した後も、忙しく、疲れてしまうものですが、離婚届を提出して、新しい戸籍が出来たら、年金分割の手続きも、速やかに済ませておきましょう。
■3号分割
3号分割をする場合には、分割する割合を決める必要がありませんから、第3号被保険者(例えば、専業主婦)であった者が、年金事務所等で手続きをします。
ただし、3号分割の場合にも、期間の制限があり、離婚してから2年以内に、年金事務所等での手続きをしなければなりませんから、その点は、注意してください。
また、合意分割の手続きをした場合には、3号分割の対象となる期間があれば、3号分割の手続きをしなくても、3号分割がされます。
上記では、ご理解いただくために、細かい点は省いてご説明を致しました。年金分割の手続きの詳細については、日本年金機構、年金事務所、共済組合、共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団等にお問い合わせいただき、ご自分での、ご確認をお願いいたします。
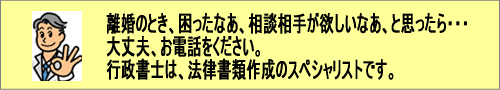

ページ名 「離婚時の年金分割 早分かり(2) 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
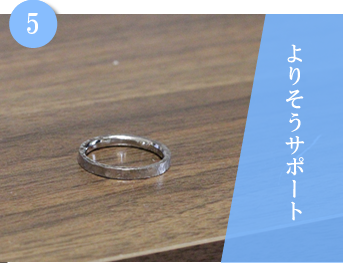
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
|
概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |


公正証書で、離婚時の年金分割のうち「合意分割」をしたいと思っています。 準備しておいた方がいいことはありますか? |
|
年金分割のうち「合意分割」をご希望でしたら、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求しておいてください。「年金分割のための情報通知書」は、請求してから届くまでに3週間~1ヶ月位かかりますし、公正証書を作成するためには必須のものですから。 |


離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか? |
|
公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。