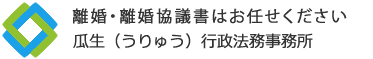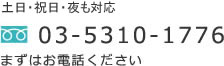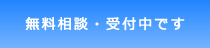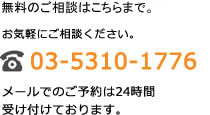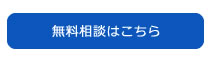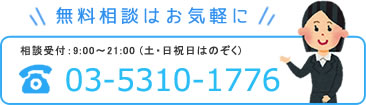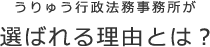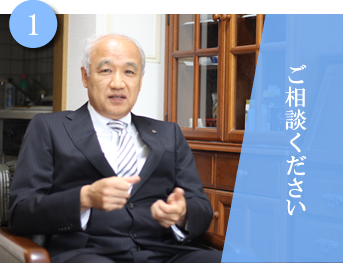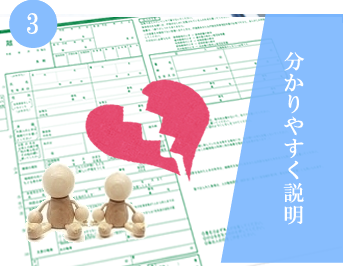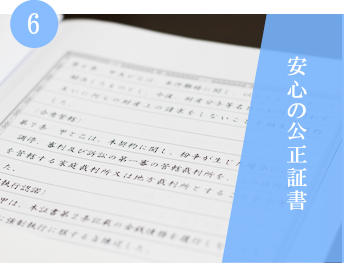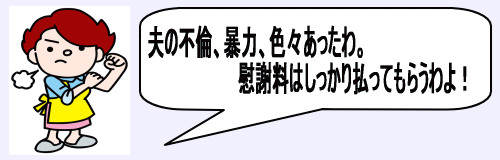
1.慰謝料とは? 離婚に伴う慰謝料の前提として
離婚をする際には、慰謝料の支払いについて決めておくこともあります。慰謝料とは、精神的な苦痛に対する賠償を言います。少し言い方を変えると、加害者が、被害者に与えた精神的な苦痛を償うために支払う金銭です。
例えば、夫に不貞行為があった場合や、夫による暴力があった場合などに、妻が被った精神的な苦痛に対する賠償として、慰謝料の支払いを決めておくというのが典型例でしょう。
2.慰謝料は、離婚の際に、常に認められるのか?
時々ありますが、離婚となれば、慰謝料をもらえると思っている方もいます。もちろん、離婚に至るまでには、苦しい思い、辛い思い、色々となさったでしょう。ただ、だからと言って、常に慰謝料をもらえることにはなりません。
離婚の際の慰謝料は、民法が定める不法行為による慰謝料の1つなのです(民法709条、710条)。ですから、慰謝料が認められるには、請求される夫又は妻に責任があるのかどうかが問題になります。責任があれば、相手が被った精神的な苦痛に対して慰謝料を支払わなければならないことになります。「夫の不倫、夫による暴力があった場合には、その夫に責任があり、妻に対して慰謝料を払う必要がある。」というのは、理解しやすいと思います。
では、性格の不一致による離婚の場合はどうでしょう。この場合にも、苦痛を感じながら生活してきたことでしょう。しかし、一般的には、慰謝料は認められていないようです。
3.慰謝料の取り決めは、離婚の際にしておきましょう。
離婚の場合、慰謝料についても離婚する際に決めておくことが通常だろうと思います。協議離婚の場合に、離婚した後で慰謝料の話しをしたくても、もう、相手は話合いに応じない可能性も高いでしょう。また、相手が話合いに応じても、離婚後に決める慰謝料の額は、離婚の際に決める慰謝料の額よりも少なくなる傾向があるという指摘もあります。やはり、離婚に伴う慰謝料については、離婚届を提出する前に決めておくことが重要です。
もちろん、離婚後に、裁判所を利用することも出来ます。但し、不法行為による慰謝料の請求は3年で時効になりますから注意が必要です。
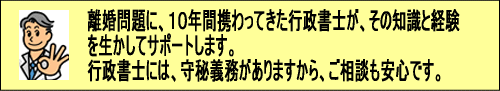
4.慰謝料に相場はあるの?
離婚に伴う慰謝料は、どのくらい支払われているのでしょうか?
これについては、どのような場合に、どのくらいの慰謝料が支払われているという明確な統計はないようです。そして、慰謝料の額は、責任の程度・結婚期間・支払う方の資力などを考慮して決めるので、相場といえるものもないようです。
ただ、平成10年度版の司法統計年報は参考になるかと思います。以下に、統計の概要を記載しますが、責任の程度・資力等が、統計の数字にどの様に反映しているのかは不明ですから、これらの数字は基準となるものではなく、あくまで参考としてご覧下さい。
まず、調停件数は2万5,144件で、財産分与・慰謝料の取決めがされたのは、1万2,038件です。比率にすると約48%となります。財産分与・慰謝料の取決めがされていない案件は、離婚するか否か・養育費等がメインだったのかも知れませんね。
財産分与・慰謝料の取決めがされた1万2,038件を見ると、金額は、その半数が50万円~400万円以下となります。平均額は、約380万円となっています。ただ、この数字には、財産分与も含まれていますから、慰謝料の金額は、この数字よりもかなり低くなると考えられます。
東京地方裁判所のデータもありますが、データ上明らかな事件は301件で、そのうち104件は慰謝料の請求が認めらていません。認められた慰謝料の額の平均は約190万円となっています。
ただ、調停にしても、裁判にしても、結婚期間が長いほど、慰謝料の金額が高くなるという傾向があります。結婚期間が長くなれば、それだけ支払う方の資力もあるということになるのでしょう。結婚期間の長さというのは、重要な要素となります。
5.分割払いになるなら公正証書の作成が良い。少なくとも書面にしておく。
慰謝料の支払いに合意し、その金額が決まったら、できれば支払いは一括で済ませたほうが良いですね。しかし、ある程度まとまった金額となるでしょうから、分割払いになることもあるでしょう。
分割払いの場合、始めは払ってくれるだろうとは思えても、1年・2年と経つと、果たして約束を守ってもらえるかどうか不安は大きいですね。分割払いにするのであれば、その約束(法律上は契約です。)を明確にするために、約束の存在・内容を文書で残してください。協議離婚の場合には、公正証書を作成しておくのが最善です。
公正証書は、法務局に所属する公証人が作成する公文書です。公証人は、裁判官・検察官等の経験のある法律の専門家で、その公証人が作成する公正証書があれば、相手が約束を守らないときには、相手の給料などの財産を差押えることができます。お金の支払いについては、公正証書は、裁判所の判決と同じ効力を持つのです。公正証書には、その様に、強い効力がありますから、相手にも「約束を守らないといけない。」という気持ちを持たせる効果もあります。公正証書を作って、その強い効力で、相手を威嚇しながら、相手に分割払いの約束を守ってもらう。分割払いの場合、できるのであれば、公正証書を作成しておきたいものです。
好評の[公正証書作成・ご相談・サポートコース] 協議離婚の際には、公正証書の作成がお勧めです。公証役場でも、離婚に関する公正証書の依頼が急増しています。そして、「夫婦共働きで忙しくて・・・」「別居していて、なかなか手続きが進まなくて・・・」という方々が、良く利用なさっているのが[公正証書作成・ご相談・サポートコース]です。
離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託などをサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。離婚後の戸籍のご相談等、公正証書以外のこともサポートしてもらえることが助かると、ご感想を頂いています。
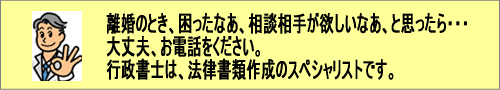

ページ名 「離婚に伴う慰謝料 離婚のときの慰謝料の解説 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
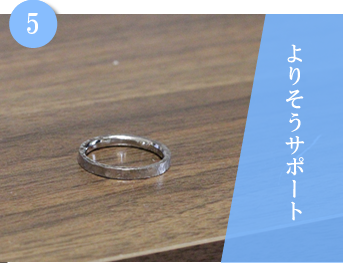
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚するのですが、夫が慰謝料を払うことを承知しました。 慰謝料の支払いがある場合も、公正証書を作っておくべきなのでしょうか? |
|
公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあります。 そこで、慰謝料の支払いを考えて見ると、例えば、離婚前に、慰謝料を一括して支払ってもらえるのであれば、もう支払いは済んでいるので、公正証書を作成するメリットはありませんね。 他方、慰謝料の支払いが離婚後になる場合には、それが一括払いでも、分割払いでも、支払が滞る恐れがありますから、公正証書を作成するメリットがあることになります。 慰謝料の支払方法がどうなっているのか、それを考えて、公正証書の作成を考えてください。 |


離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
|
概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |


公正証書を作りたいのですが、代理人によって、公正証書を作ることはできますか? |
|
代理人によって公正証書を作ることもできます。 遠く離れて暮らしている、相手の顔を見たくない等、色々なご事情で、相手の方と一緒に公証役場へ行けないことがあります。 そのような時には、代理人を使って公正証書を作ることができます。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。