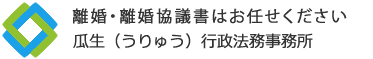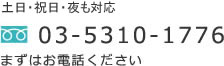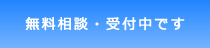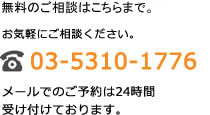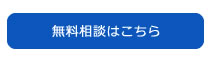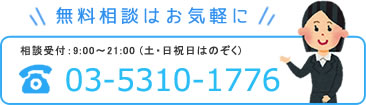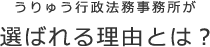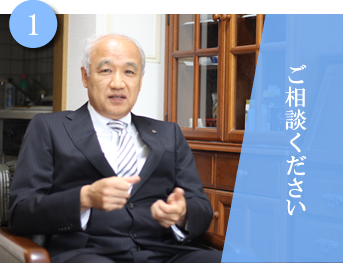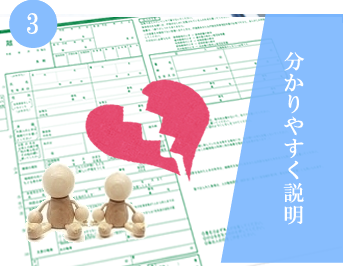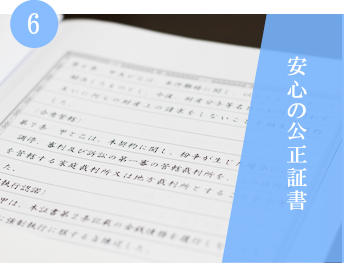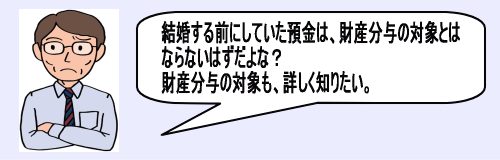
1.財産分与の対象となる財産
財産分与(清算的財産分与)とは、結婚中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することを言いますから、財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力によって築いた全ての財産です。名義は、夫名義・妻名義いずれでも財産分与の対象となります。
従って、預貯金・不動産・株式・美術品・自動車・家具・電化製品等が財産分与の対象となりえます。

財産分与の対象となる不動産に住宅ローンが残っている場合には、売却して清算するにしても、また、ご夫婦のどちらかの所有とするにしても、残っているローンの支払い・不動産の利用方法などについてケース毎に慎重な検討が必要になります。
2.退職金
退職金は、財産分与の対象となるのでしょうか?
(1)離婚の時までに、退職金を受け取っていて、預金している場合には、財産分与の対象となります。
(2)離婚時に、支給が決定されている退職金も財産分与の対象となるとされています。
(3)問題は、将来の退職金ですが、これについては近い将来に支給される可能性が高い場合には、財産分与の対象となるとされています。
「近い将来」の時期については、2~3年くらいという指摘もありますし、地方裁判所の判決では、6年後の退職金を財産分与の対象としたものもあります。
3.離婚時の年金分割制度
年金分割については、新聞等で盛んに報道されましたが、誤解していらっしゃる方も少なくないようです。概略だけを載せますので、詳しくは日本年金機構のホームページで是非ご確認ください。
(1)平成19年4月以後に離婚した場合には、妻は、夫婦の合意または裁判所の決定があれば、夫の厚生年金の2分の1を限度として、自己の年金として受け取れるようになりました。
(2)平成20年4月からは、専業主婦が離婚する場合、夫の厚生年金の2分の1を自動的に受け取れるようになります。
詳しくは、社会保険庁のホームページをご覧ください。
4.財産分与の対象とならない財産
以上のように、結婚中に夫婦が協力して築いた財産は、財産分与の対象となりますが、それに対し、特有財産または固有財産と言われるものは、財産分与の対象とはされないのが原則です。
具体的には、(1)結婚前にしていた預金 (2)結婚する際に父母からもらった財産 (3)父母・兄弟が亡くなったために取得した相続財産等です。
これらは、原則として、結婚中に夫婦が協力して築いた財産とは言えず、財産分与(清算的財産分与)の対象にはされないのです。
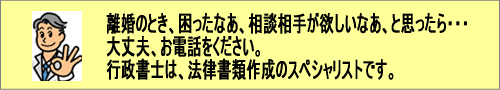

ページ名 「財産分与の対象となる財産は? 離婚後の安心をサポートさせていただきます」
文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦
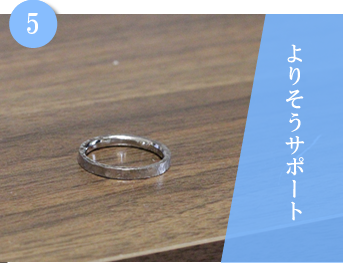
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
よくある質問 相談について
離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
離婚するのですが、財産分与として金銭の支払いがあります。 このような場合も、公正証書を作るべきでしょうか? |
|
公正証書は、支払金額と支払期限が決まっている約束をしたにも拘わらず、金銭の支払いが滞ったときに、強制執行の根拠になります。支払を強制できるという点で、ここに公正証書を利用するメリットがあるのです。 そうすると、財産分与としての金銭の支払いが、離婚前に済むのであれば、支払が滞ることはありませんから、公正証書を作成する必要はありませんね。 他方、財産分与としての金銭の支払いが、離婚後となるのであれば(一括払いでも、分割払いでも)、支払が滞るおそれがありますから、公正証書を作成しておく必要があります。 |


離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |
|
概略、以下のようになります。
*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |


離婚の公正証書を作った時には、「送達」をしておいた方がいいのでしょうか? |
|
公正証書で強制執行するためには、強制執行を開始する前に、公正証書の謄本(コピー)を債務者(養育費や慰謝料を支払う方)へ送る必要があります(これを、「送達」と言い、公証人が送ります)。「この約束を忘れていませんか?」と通知するためで、最後通牒のようなものです。
ただ、公正証書の場合には、特殊な対応が認められています。つまり、公正証書を作る時に、債務者が公証役場に来るのであれば、その場で、債務者へ謄本を渡して、受取を作ることで、この送達を終わらせることができます。これを、「交付送達(または、公証人送達)」と言います。 公証役場の実務では、交付送達が行われのが、通常だと思います。特に、離婚で、養育費の支払いが約束される場合には、養育費の支払い期間が長くなり、債務者の住所などが分からなくなる恐れもありますから、公正証書を作った時に、「交付送達」をしておくことをお勧めします。 |
ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。